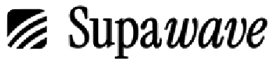まずは簡単に自己紹介をお願いします。
メインの仕事は製薬会社勤務です。家族が大阪に住んでいて、東京と行ったり来たりで生活しています。
売薬業が盛んだった富山県の出身で、薬は幼い頃から身近でした。飲むと症状がなくなる体験から「薬ってすごいな」と神秘を感じ、惹き寄せられるように興味を持ちました。
北海道大学の薬学部に進学し、がんや免疫の研究で博士号を取得しました。
理化学研究所を経て、その次に約7年間在籍したのがハーバード大学医学部です。いわゆるポスドクという立場で、教授の研究予算から給料をもらい、研究して論文を出す職人のような仕事です。競争は激しかったですが、僕は憧れだった海外生活を送れて楽しい面も大きいと感じていました。
反面、帰国してからは三重大学で独立助教のポジションにつきましたが、あまり楽しいと思えませんでした。
考えるうちに自分の道は研究者以外にもあるのかもしれないと思い、助教を1年で辞めて、2014年に外資系の製薬会社に転職しました。それからはずっと製薬業界にいます。今は4回目の転職をして2か月ほどです。
製薬会社ではどんな仕事をしていますか?

社外と協力しながら新しい薬を創るプロジェクトに関わっています。
かつては製薬会社が大きな研究所を持っていましたが、社内での研究開発は資金面でも時間面でも効率が悪いのです。
研究の成果が出て売り出されるまでは10~15年ほどと長期間です。巨額の投資をした後でダメだと分かることもあります。さらには、十分に良い薬が他社から売り出された、病気自体が駆逐されたなど、開発していた薬が不要になることもあります。
そこで僕が製薬業界に入った当時、海外で流行していたのが、オープンイノベーション方式です。面白い研究をしている大学の先生と提携して、知財などを共有しながら薬づくりをするのです。
日本でもオープンイノベーションの波が来ていると感じたのが、製薬会社への転職を選んだ理由の1つでした。研究の状況を見に行ったり、教授から声をかけてもらえるような関係を作ったり、プロジェクトの契約を結んだりする仕事です。
今は大学の先生よりも、大学の先生が作ったスタートアップ企業などで基礎的な部分を実施してもらい、臨床試験段階のプロジェクトをライセンス購入するパターンが増えています。
サブのお仕事についても聞かせてください。

2020年、もともと自由度が高めな働き方でしたが、コロナ禍で在宅勤務が増え、時間に余裕ができました。そのとき、Project MINTというコミュニティの後押しがあって、副業を始めました。
ライフサイエンス分野のコンサルティングやスタートアップ企業のメンタリング、大学での講演、コーチング、ズンバインストラクター、英語コミュニティの運営。
それと2024年の終わりからは化粧品会社の代表をしていて、2025年後半は慶応大学のMBAコースメンターに呼ばれています。
どんなきっかけで事業を広げていったのですか?
プロボノでベンチャーキャピタルのアドバイザーに入ったのが最初です。製薬業界の知見を活かして、バイオテック企業の評価をしていました。
また、ちょうどコロナ禍でアメリカの企業が日本に渡航できなかったので、友達経由で依頼が来たのが、日本のライフサイエンスエコシステム現状調査のコンサルタントです。
さらに1~2年の間にスタートアップ企業のメンタリングも開始し、個人事業として屋号を持つようになり、少しずつ拡大していきました。
その結果、出身の北海道大学から講演の声がかかるようになりました。テーマは「キャリアのつくりかたとPhD」「効果的なプレゼンテーション」「コラボレーションと信頼」などです。今は大学1年生に向けて、「楽しく仕事をして生きていくためのマインドセット」も話しています。
化粧品会社は、大学生のときに家庭教師をした家庭の、僕を息子のようにかわいがってくれていたお母さんから託されたものです。10年以上の歴史があり、プロダクトもあって、ただマーケティングをあまりしていない。代表2名だけの小さな会社です。
体制の移行、決算などが落ち着いて、今はウェブサイトの立ち上げ直しやECについて検討を進めています。アミテインハーブというブランドで、敏感肌の方に人気です。
英語コミュニティは仲間の先生と一緒にやっています。コミュニティで毎月無料のzoomセッションを開催して、海外ドラマのワンシーンを深掘りしたり、英語プレゼンについて解説したり、いろいろなコンテンツを発信中です。
コーチングはなぜ始めたのですか?

機会があって学んでみたらとても役に立ったからと、海外生活や外資系勤務を通じて感じた日本の組織の呪縛を解きたいと思ったからです。
結局、個人の特性が生きていないと、良い組織にはならないんですよね。もっと個を発揮したほうが良いのに、サラリーマンの多くは、転職は怖い、副業をして会社に怒られるのが怖いと言います。
今は個人向けのコーチングや、レゴブロックを使ったチームビルディングを提供しています。今後は、経験豊かなコーチ仲間と一緒に、チームや会社の組織に向けた組織変容プログラムを提供しようと企画中です。
なぜズンバだったのですか?

子どもの頃からダンスや歌が好きでした。大人になって「稼ぐ」事を優先してそんなことも忘れていましたが、40歳手前になって改めて体を動かそうと思ったとき、ズンバに出会って、すっかりハマりました。長らくいちズンバファンでしたが、次第に好きが高じてインストラクターになっていました。
そんなとき、asobijiというコミュニティを主催している友人が企画してくれたのが、僕の初めてのズンバ教室です。人を呼び集めてくれて、値段設定や集金もしてくれました。
やってみたらとっても好評で僕自身も楽しくて。それ以来、月1回くらいのペースで3年ほど続けています。
最初は渋谷で、今は三軒茶屋。三軒茶屋のスタジオはズンバの後はバーへと変わるんです。踊った後にお酒を飲んで交流できるのが大好評ですよ。
今後、何を大切にして活動を展開しますか?

スペインのガルシア氏とミラージェス氏は、好きで、得意で、お金がもらえて、かつ世の中から歓迎される、4つを満たしていることが「IKIGAI」だと言っています。
製薬会社の仕事はお金にもなり、世の中に貢献もしていて、得意でもあるけれど、楽しさは程々。ズンバはお金にはあまりならないけれど、心が踊る楽しさはケタ違いです。他の様々な仕事にもそれぞれに違う良さがあって、全てをひっくるめたポートフォリオとして自分の幸せを最大化しています。
その背後には、人生はロールプレイングゲーム、成長ゲームだという考えがあります。僕のIKIGAIとはこのゲームを楽しんでいくことです。
同時に、人生100年時代、会社の定年退職後も楽しめる人生を用意しておくため、今のうちからいろんな種まきをし、助走をつけておきたい気持ちもありますね。