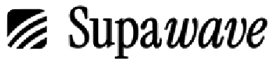パタゴニアの創業者であるイヴォン・シュイナードは、ビジネスマンをゲス野郎と呼ぶことで知られており、自分がビジネスマンであることを恥ずかしいと思うこともよくあると述べています。
実際、彼は自分自身のことを「意図せずしてビジネスをしてしまったクライマー」だと述べている。
もちろん、何もするにしても、お金がかかるわけなので、誰でも何かしらの手段でお金を稼ぐ必要があることでしょう。
しかし、誰もが当たり前に自分のことを起業家、経営者、ビジネスマンなどと呼ぶようになってしまったことで、既に起業や経営という言葉自体がコモディティ化してしまっている。

意図せずしてビジネスをしてしまったクライマー
もし、今後AIによって、世の中の生産性が格段に上がり、業務コストが下がってくるとするならば、これまでは当たり前であった経済合理性が働かなくなっていく。
つまり、これまでは、自分の限りある時間を何に使うか、どんな仕事に就くか、何を購入するかという判断の基準は「儲かる」かどうかで決められていましたが、これからは、どの選択肢が自分にとって「居心地が良いか」という基準になっていくのでしょう。(1)
現在では、多くのビジネスマンが居心地の良さではなく、利益のために読書をし、契約のためにパーティーに参加して、人脈のためにランチをしている。
儲かるかどうかという視点で考えると、TOEICの点数が高い、プログラミングができる、会計士の資格を持っているなどといったスキルを軸にその人を見ていきます。
それに対して、その人と一緒に居て居心地が良いかという視点で考えると、コミニケーション、芸術、笑いなどといった言語化、数値化できないセンスを軸にその人を見ていくことになるのです。

「儲かるか」の基準から「居心地が良いか」という基準へ
「サピエンス全史」の の著者ユヴァル・ノア・ハラリは、「現在、子供が学校で習っていることの80〜90%は子供たちが40代になる頃、ムダになっている可能性が高い。一方、休み時間に学んだことの方が、大人になってから役に立つだろう」と述べました。
これは、仕事も同じことなのかもしれない。
会社の中で学んだことなど、すぐに役に役に立たなくなる可能性が高い。
逆に自ら能動的に動き、会社の外での繋がりや仕事とは全く関係のない遊びを通じて得た知恵などの方が、意識しなくても実際にビジネスに役立ってしまうものなのだろう。
「儲かる=スキル」、「居心地の良さ=センス」、でも、結局、パタゴニアの創業者のように、ビジネスマンを否定したとしても、センスのある人が一番儲かってしまうのかもしれない。