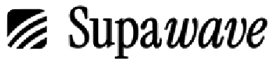心理学者のディーン・キース・サイモントンの1977年の研究によれば、さまざま文化において、並外れた業績が生み出される時というのは、民族の大きな移動があった後なのだと言う。
旅行や仕事などでの移動は、最も効果的に脳に刺激を与える方法の一つ。
本田宗一郎は、特に用が無くても、常に移動していないと気がすまい「動的人間」でした。
一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏は、本田宗一郎について「身体で物事を考える知的野蛮人」だったと述べている。(1)
亡くなる二日前であっても、「自分を背負って歩いてくれ」と妻に言い、点滴をつけたまま病院内を歩き回っていたのだと言います。

移動は最も効果的に脳に刺激を与える方法の一つ。
これからは、企業でもイノベーションを起こしたければ、研究費ではなく旅費に予算をつけるべきなのかもしれない。(2)
どんな新しいことも、最初は人と人との小さな対話から生まれる。
それも社内の人たちとの対話ではなく、都市や田舎など自分から遠く離れて暮らしている人達や全く違う業界で働く人との会話から大きなヒントが生まれることが多い。
常に移動し続けることが前提になっていくと、人間関係が固定されず、自然と流動的なものになっていきます。
これまでは、「移動する=人と離れる」というイメージだったのかもしれませんが、これからは移動すればするほど、どんどん人と繋がっていく時代になっていくのでしょう。(3)
シン富裕層と呼ばれる人たちが、一番大切にしている価値観は、資産の額ではなく「時間」と「移動性」で、この二つを最大限活用して、時間と場所にとらわれないライフスタイルを目指していくのです。

富裕層が意識するのは、「時間」と「移動性」
SNSで有名な発信者をフォローすると、これまで自分にはなかった新しい視点を持つことができます。
これは移動も同じことで、場所が変わることでChatGPTの回答からは決して得ることのできない新しい「視座」や「欲望」を見つけることができるのです。
イギリス人作家のデイビッド・グッドハートは、世界は「anywhereの人々」と「somewhereの人々」に二分化されつつあると述べました。
「anywhereの人々」とは世界中どこでも勝負できる人達。
一方、「somewhereの人々」とは、生まれた育った場所でしか働けない人達で、週末も自宅から半径20キロ以内でほとんどの物事を済ませようとします。

移動によって新しい「視座」や「欲望」を見つけ出す。
恐らく、これからは移動し続けることで、新しいアイディアをどんどん出していける人と、半径20キロ以内しか移動せず、固定された人間関係の中で少しずつ衰退していく人達の二極化がどんどん進んでいくことでしょう。
自分のやりたいことが分からなかったら、とにかく移動して、新しい人に会ってみるというフットワークの軽さが、これからは成長に求められる一番大切なスキルになっていくのかもしれません。