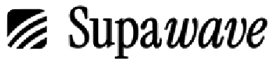民藝運動の主唱者として知られる思想家の柳宗悦氏は、「新幹線ができたら、移動が早くなりすぎて、窓から地域の風景や人々の暮らしが見えなくなるだろう」と言いました。
また、世界的な投資家として知られるウォーレン・バフェットも「スマートフォンは自分には“スマート過ぎる”から必要ない」と言って、長年、ガラケーを愛用していたことは良く知られています。
スマートシティ、スマートホーム、スマート家電、スマート支払いなど、テクノロジーの発展によって、世の中にはスマートという言葉が溢れかえっている。

↑「スマート」は本来得るべき体験までも奪っていく。
「スマート」であることの条件として、「労力がかからないこと」や「早く結果が得られること」などがあげられます。
しかし、スマートなことの押し付けに慣れてしまうと、様々な手間を通じて、人間が本来得るべき体験が根こそぎ失われてしまう。(1)
スマートなものを取り入れる際には、私たちは明確な意図を持たなければならず、本来、手間を通じて得られるはずであった人間の努力、創造性、生産性、目的、意味、そして、達成感などを奪うものであってはならないのだろう。
むしろ、スマートなものを取り入れることによって、こういったものを増幅させていかなければならない。
何かを成し遂げたことがある人であれば、当然分かることですが、本当に価値のあることは、効率の悪いプロセスを通じてしか獲得できません。

↑本当に価値のあることは、効率の悪いプロセスからしか生まれない。
スマートなものをいち早く取り入れ、競争に勝とうとするよりも、自分を律することで、周りと距離をとりながら、新しい意味を生み出していく方が何倍も難しい。
電車に乗る時間が増えたら、運動する時間を増やす、SNSやオンラインMTGの時間が増えたら、地域や近所の集まりに参加してみるなど、一つスマートなものを導入したら、アナログや不便なものを一つ増やすくらいの意識でいないと、人間が本来体験すべきものがどんどん失われていってしまいます。
AI時代は、どれだけスマートに生きるかよりも、面白さやキャラクターが重視され、非合理な部分にこそ個性が宿る。
スマートの押し付けによって、人間が本来得るべき体験を失わせてはならない。